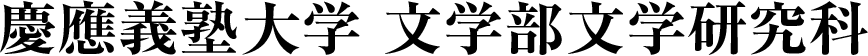- ホーム
-
イベント一覧
イベント一覧
Featured Events
-
東アジア地域漢文学総合討論 동아시아 지역 한문학 종합토론
日程:2025/12/19(金)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 東館4階 オープンラボ対象:事前申込不要です。ご自由にご参加ください。 -
日程:2025/11/29(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 南校舎445教室対象:会場開催についてはどなたでもご自由にご参加いただけますが、ZOOMでの視聴を希望される場合は、11月28日(金)までに以下のフォームより必ずご登録ください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoy8VIg71zLvVdA6KkD4bMg9-03dH6gVhu2zrdxu52ccaKug/viewform -
日程:2025/11/29(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 東館6階 G-ラボ(オンライン併用)対象:どなたでもご参加いただけます。事前の参加申込みが必要です。
-
日程:2025/11/08(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 東館6階 G-Lab(オンライン併用)対象:
-
三田図書館・情報学会第196回月例会「図書館特別資料の段階別管理・活用と次世代司書育成プログラム」
日程:2025/10/25(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 南校舎4階445教室(オンライン併用)対象:どなたでもご参加いただけます。事前の参加申込みが必要です。 -
日程:2025/07/19(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 第一校舎101号室/Zoom配信あり対象:会場開催についてはどなたでもご自由に参加いただけます。ZOOMでの視聴を希望される方は、7月18日(金)までに申込みフォームより必ずご登録ください。
-
第一屆亞洲漢文學研究跨國學術會議「2025 亞洲漢文學研究 地域‧文人‧文脈」
日程:2025/07/10(木)、2025/07/11(金)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 東館/対面のみ対象:事前申込不要です。ご自由にご参加ください。 -
三田図書館・情報学会特別月例会「iSchool@Illinois: 図書館情報学の過去・現在・未来」(発表者:J. Stephen Downie(イリノイ大学情報学部教授・ 研究担当副学部長 ))
日程:2024/12/26(木)場所:慶應義塾大学三田キャンパス内(詳細は後日)・オンライン併用対象:どなたでもご参加いただけます。事前の参加申込みが必要です。 -
G. Stocker教授、W. Kriegleder教授 特別講演会
日程:2024/12/10(火)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 南館9階ディスカッションルーム対象:入場無料、事前予約不要 -
日程:2024/11/30(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 西校舎 527教室対象:会場開催についてはどなたでもご自由にご参加いただけますが、ZOOMでの視聴を希望される場合は、11月28日までに以下のフォームより必ずご登録ください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoy8VIg71zLvVdA6KkD4bMg9-03dH6gVhu2zrdxu52ccaKug/viewform
-
日程:2024/11/09(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 東館6階 G-Lab(オンライン併用)対象:
-
三田図書館・情報学会第194回月例会「北欧の公共図書館における移民・難民の背景を持つ家庭を主対象としたブックスタートの展開」(発表者:和気尚美氏(慶應義塾大学文学部))
日程:2024/09/21(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス研究室棟1階AB会議室(オンライン配信も併用)対象:どなたでもご参加いただけます。三田図書館・情報学会会員は無料/非会員は1,000円。事前の参加申込みが必要です。 -
DH国際ワークショップ「人文学と3D/3D Scholarly Editing」
日程:2024/09/17(火)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 東別館9階対象: -
三田図書館・情報学会第193回月例会「情報資源組織化と計算可能性:デジタルアーカイブの将来に向けて」(発表者:永崎研宣氏(慶應義塾大学文学部))
日程:2024/08/03(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス研究室棟1階AB会議室(オンライン配信も併用)対象:どなたでもご参加いただけます。三田図書館・情報学会会員は無料/非会員は1,000円。事前の参加申込みが必要です。 -
日程:2024/07/20(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 第一校舎 101教室対象:
参加費:無料
当日は、ZOOMによる中継も行います。
会場開催についてはどなたでもご自由にご参加いただけますが、ZOOMでの視聴を希望される場合は、7月18日までに以下のフォームより必ずご登録ください。https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoy8VIg71zLvVdA6KkD4bMg9-03dH6gVhu2zrdxu52ccaKug/viewform
-
慶應義塾大学三田哲学会・連続講演 音としての「精神」― 音楽を通して「近代」を再考する・第七回 夢は何処へ
日程:2024/05/22(水)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 北館ホール対象: -
DH国際ワークショップ「デジタル漢文研究ーデジタル手法の最前線ー」
日程:2024/05/11(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 南校舎445対象: -
三田図書館・情報学会 橋本孝先生記念講演「学術コミュニケーションの現状と将来:学術出版からオープンサイエンスへ」(発表者:倉田敬子氏(慶應義塾大学文学部))
日程:2024/03/16(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 東館6階G-Lab(オンライン配信あり)対象: -
日程:2024/01/29(月)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 東館4階オープンラボ対象:事前登録不要・参加費無料
-
三田図書館・情報学会 橋本孝先生記念講演「図書館目録メタデータの現在地~概念モデルからリンクトデータまで」(発表者:谷口祥一氏(慶應義塾大学文学部))
日程:2024/01/20(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 南校舎4階447教室対象: -
慶應義塾大学久保田万太郎記念資金 記念誌刊行記念シンポジウム「久保田万太郎と現代」
日程:2023/12/16(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス北館ホール対象:どなたでもご参加いただけます。(対面開催、入場無料、予約不要) -
日程:2023/11/11(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 東館6階 G-Lab対象:
-
日程:2023/11/04(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 南校舎 453番教室対象:
参加費:無料
当日は、ZOOMによる中継も行います。
会場開催についてはどなたでもご自由にご参加いただけますが、ZOOMでの視聴を希望される場合は、11月2日までに以下のフォームより必ずご登録ください。https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoy8VIg71zLvVdA6KkD4bMg9-03dH6gVhu2zrdxu52ccaKug/viewform
-
三田図書館・情報学会第192回月例会「北欧のスマートシティ~ハブとしての公共図書館~」(発表者:安岡美佳氏(ロスキレ大学))
日程:2023/09/23(土)場所:オンライン開催対象:どなたでもご参加いただけます。三田図書館・情報学会会員は無料/非会員は1,000円。事前の参加申込みが必要です。 -
三田図書館・情報学会第191回月例会「生成AIと研究・教育へのインパクト」(発表者:宮田洋輔氏(慶應義塾大学文学部)、田島逸郎氏(Georepublic Japan)、宮川創氏(国立国語研究所))
日程:2023/07/29(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 研究室棟1階AB会議室(オンライン配信も併用)対象:どなたでもご参加いただけます。三田図書館・情報学会会員は無料/非会員は1,000円。事前の参加申込みが必要です。 -
日程:2023/07/15(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス北館ホール(1階)対象:
どなたでも、事前申し込み要
オンライン同時配信あり
-
-
日程:2023/07/08(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 第一校舎 122番教室対象:
参加費:無料
当日は、ZOOMによる中継も行います。
会場開催についてはどなたでもご自由にご参加いただけますが、ZOOMでの視聴を希望される場合は、7月6日までに以下のフォームより必ずご登録ください。https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoy8VIg71zLvVdA6KkD4bMg9-03dH6gVhu2zrdxu52ccaKug/viewform
-
日程:2023/07/07(金)場所:慶應義塾大学 三田キャンパス 北館1階 北館ホール対象:どなたでもご参加いただけます
-
日程:2023/06/10(土)場所:オンライン・ライブ配信(Zoom Webinar/予約不要)対象:どなたでもご参加いただけます
-
慶應義塾大学三田哲学会・連続講演 音としての「精神」― 音楽を通して「近代」を再考する 第6回 劇場の世界
日程:2023/05/24(水)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 北館ホール対象:入場無料・申込制(下記URLからお申込みください)
-
日程:2023/03/11(土)場所:オンライン開催対象:どなたでも無料でご参加いただけます。参加申込みが必要です。
-
三田哲学会 講演会 「社会の中での行為をささえる積極的な脳 Enactive Brainの理解を通して、人間の「学びと成長」を考える」
日程:2023/03/10(金)場所:慶應義塾大学三田キャンパス西校舎516教室対象: -
三田哲学会 ワークショップ 「責任のありかと、そのゆくえ――徹底討議・瀧川裕英×斎藤慶典 」
日程:2023/03/08(水)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 南館地下4階 ディスタンスラーニングルーム対象:どなたでも参加できます。要事前登録(登録詳細は追ってお知らせします)オンライン中継はありません。 -
構築される「遺跡」:KeMCo建設で発掘したもの・しなかったもの
日程:2023/03/06(月)~ 2023/04/27(木)場所:慶應義塾ミュージアム・コモンズ(三田キャンパス東別館)対象:どなたでもご覧いただけます -
日程:2023/03/04(土)場所:慶應義塾大学 三田キャンパス 東館・Gラボ(6・7階)オンラインにてZoom配信可能(登録者にパスコード配布)対象:どなたでも無料でご参加いただけます。事前の参加申し込みをお願いします。登録期限は対面参加は2月26日(日)、オンライン参加は3月2日(木)
-
日程:2023/02/02(木)場所:慶應義塾大学三田キャンパス研究室棟 AB会議室対象:どなたでもご参加いただけます。
-
日程:2023/01/17(火)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 西校舎 515教室対象:どなたでもご参加頂けます。
-
日程:2022/12/03(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 第一校舎 121番教室対象:
参加費:無料
当日は、ZOOMによる中継も行います。
会場開催についてはどなたでもご自由にご参加いただけますが、ZOOMでの視聴を希望される場合は、12月1日までに以下のフォームより必ずご登録ください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoy8VIg71zLvVdA6KkD4bMg9-03dH6gVhu2zrdxu52ccaKug/viewform -
三田哲学会講演会「 異界/異世界の概念形成に向けて:現代都市伝説に見る非日常的空間の分類学 」
日程:2022/12/02(金)場所:慶應義塾大学三田キャンパス(開催教室は現在調整中)およびZoomによるハイブリッド形式対象:どなたでもご参加いただけます。(追って参加申し込みURLをお知らせします。) -
日程:2022/11/12(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 東館6階 G-Lab対象:
-
ワークショップ「パフォーマンス・アートのワークショップ」(三田哲学会主催)
日程:2022/11/04(金)場所:三田キャンパス南校舎457 および 中庭対象:三田哲学会員の方 -
『横浜[出前]美術館:学芸員によるレクチャー「ミュージアム・コレクションの未来」』
日程:2022/10/29(土)場所:日吉キャンパス来往舎1階 シンポジウムスペース対象:12歳以上(参加費無料・要申込) -
三田哲学会講演会「エスニック・アートの『作者』は誰か?:台湾原住民族の織物、熟練、オーサーシップ」
日程:2022/10/07(金)場所:慶應義塾大学三田キャンパス(会場は現在調整中)およびZoomによるハイブリッド形式対象:どなたでも参加できます。
参加ご希望の方は、下記URLより【2022年10月6日(木)正午まで】に必ずご登録をお願いします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxW1uHSj2ISzJQBALEllaXNX3Ei7eDEjdKiDbLCa3gRYYCgA/viewform?usp=sf_link開催場所の詳細については、ご登録いただいたメールアドレスに後日案内を送付いたします。Zoom URLは前日までにお送りします。
-
第189回三田図書館・情報学会月例会「デジタル社会における出版の民主化と図書館に期待される役割の変化」(発表者:鷹野凌氏(NPO法人HON.jp)、コメンテーター:間部豊氏(帝京平成大学))
日程:2022/09/24(土)場所:オンライン開催対象:どなたでも無料でご参加いただけます。参加申込みが必要です。 -
ワークショップ「私は自由なのか――徹底討議・青山拓央×斎藤慶典」(三田哲学会主催)
日程:2022/09/23(金)場所:オンラインでの実施対象:どなたでもご参加いただけます。※事前登録制
なお、参加にあたっては、以下の事前申し込み用のフォームに必要事項をご記入ください。
確認ができ次第、折り返し、当日のオンライン会場へのアクセス情報をお送りいたします。
https://forms.gle/jvucRL9scR6kj2o4A -
第188回三田図書館・情報学会月例会「情報教育と学校図書館の結びつき:GIGAスクール構想を背景として」(発表者:今井福司氏(白百合女子大学基礎教育センター)、中園長新氏(麗澤大学国際学部))
日程:2022/07/30(土)場所:オンライン開催対象:どなたでも無料でご参加いただけます。参加申込みが必要です。 -
日程:2022/07/30(土)場所:南校舎432(参加自由)対象:どなたでも参加いただけます
-
日程:2022/07/28(木)場所:南校舎455対象:三田哲学会員の方
-
【文学研究科】専攻・分野別入学説明会・相談会のお知らせ(7/9(土)16:15~)
日程:2022/07/09(土)場所:慶應義塾大学三田キャンパス 南校舎対象:申込不要
各教室まで直接お越しください