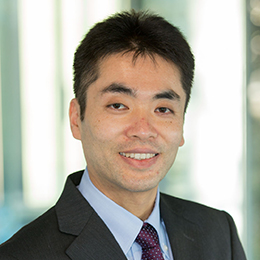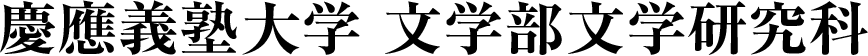Asian History
概要
東洋史研究の対象は一般的にアジアと呼ばれる地域ですが、問題設定の方法、時代によってはアフリカやヨーロッパもその視野に入ってきます。中東イスラーム世界の歴史研究を志す人にとって、マグリブやバルカンも重要地域であり、華人のネットワークに興味をもつ人は、アジアのみならずアメリカやヨーロッパも視野に入れなければなりません。
東洋史の魅力は、このような広大な対象地域にあるといっても過言ではありません。しかし、専門性を重視する大学院においては、広く浅く学ぶというやり方は避けなければなりません。そこで東洋史学分野では、これまでの学問的な伝統と、史料を読むツールとしての語学などとの関係から、以下のように対象を東西二つの領域に分けています。それぞれの領域で完結性の高いカリキュラムを組み、深く学べるようになっています。
一つ目の領域は、中国を中心とする東アジア史研究です。ここには中国古代史研究と、史料を重視する実証主義史学や文献史学の伝統に基づく、明清から人民共和国期にかけての中国近現代史研究が含まれます。前者は松本信広以来の学統である民俗学の手法を取り入れたもの、後者は明治から大正期にかけて日本を代表する東洋史学者であった、田中萃一郎によって切りひらかれたものです。また、日本と中国および世界の華人ネットワークを視野に入れた都市社会史や文化交流史も、もう一つの柱になっています。
二つ目の領域は、アラブ、トルコ、イラン、中央アジアなどの中東イスラーム世界史研究です。かつてこれら諸地域の研究は、中国の辺境史としての位置づけしか与えられてきませんでした。しかし、今では世界をとりまく情勢が変わり、緊急にして最重要な分野として誰もが認めるようになっています。本塾ではこの分野におけるパイオニアである前嶋信次、井筒俊彦の学統を継承しながら、アラブでは社会史研究に、非アラブではオスマン帝国史研究に重点をおきながら研究・教育を行っています。
以上は教員サイドから見た特徴と言えるものですが、院生は基本的に自分の好きなテーマで研究が行えるようになっています。自分の頭と身体でアジアを知り、師を越えるという気概を持ち、自らの手で新しいフロンティアを探りあて社会に巣立って欲しいという思いがあるからです。そのために、外部から多彩な講師陣を招いて知的刺激の拡充に努める一方、社会に出てから場合によっては欧米系の言葉以上に有力な武器となる、東西のアジア系諸言語を存分に学べるカリキュラムが用意されています。
教員
名前/職位
専攻/専門領域/研究内容/主要著作
-
東洋史学専攻
東アジア近現代史、食の文化交流史、中国都市史上海をおもなフィールドとして、近代都市の社会変動を研究しました。また、食の文化交流をテーマとして、20世紀以降のナショナリズムが中国料理をどのように変えたのか、日本の帝国主義が中国料理の受容にどのように影響したのかを考えました。近年では、現代中国における地方料理の形成や、中国・日本・韓国料理のアイデンティティの歴史にも関心をもっています。各都市の雑誌・新聞や行政・企業文書を精査・照合し、さらにインタビュー調査を補充して、できるだけ多くの具体例を検証するように心がけています。
主要著作- 『上海大衆の誕生と変貌:近代新中間層の消費・動員・イベント』(東京大学出版会,2012)(葛涛・甘慧杰訳『上海大衆的誕生与変貌:近代新興中産階級的消費,動員和活動』上海辞書出版社,2016)
- 『中国料理と近現代日本:食と嗜好の文化交流史』(編著書,慶應義塾大学出版会,2019)
- 『中国料理の世界史:美食のナショナリズムをこえて』(慶應義塾大学出版会,2021)
- “From Chinese food to Japan’s Hokkaido heritage: The transformation of the grilled mutton or lamb dish ‘Jingisukan,’” in Routledge Open Research: Culinary Heritage, 25 June 2024, doi: https://routledgeopenresearch.org/articles/3-2
- “Forgotten Imperial Culture: The Spread of Taiwanese Oolong Tea in Early Twentieth-Century Japan,” in Taiwan Historical Research (《臺灣史研究》, Institute of Taiwan History, Academia Sinica, Taiwan), Vol. 31, No. 3, September 2024, pp. 77–130.
-
東洋史学専攻
中近世中東社会史、アラブ都市史、地中海交流史エジプト、シリア、アラビア半島を視野の中心に据え、アラブ地域の中近世史を研究してきました。現在は、オスマン帝国期とフランス占領期のエジプトにおける都市や村落の政治・社会・経済・文化の多角的な解明をめざして、地方都市マハッラ・クブラーのイスラーム法廷記録を読み解いています。また、近世カイロの無名の計量人が記した歴史書の研究も進めています。
主要著作- 『中世環地中海圏都市の救貧』(編著、慶應義塾大学出版会、2004)
- 『オスマン帝国治下のアラブ社会』(単著、山川出版社、2017)
- 『地中海世界の旅人:移動と記述の中近世史』(編著、慶應義塾大学出版会、2014)
- 『ナイル・デルタの環境と文明Ⅰ・Ⅱ』(編著、早稲田大学イスラーム地域研究機構、2012-13)
- 『岩波講座世界歴史10 イスラーム世界の発展』(共著、岩波書店、1999)
-

東洋史学専攻
オスマン帝国史、中東都市社会史オスマン帝国期を中心とする前近代の中東諸都市において、人々がどのように生活していたかという問題に関心があります。現在は、都市民の多数を占める商人や職人に着目し、オスマン帝国期のイスタンブルを中心に商工民や同職組合について研究をしています。商工民の生活や同職組合の運営の実態を解明するため、主に未刊行史料であるイスラーム法廷記録から関連する事例を抽出し、それらの解読と分析を進めています。また、同様の問題関心から、当時の娯楽や消費文化、慈善・救貧活動・相互扶助などに関する研究にも取り組んでいます。
主要著作- 「一八世紀イスタンブルにおける皮鞣工イブラヒムの遺産とその相続」(『史学』88巻3・4号、2020年)
- 「近世オスマン帝国都市の慈善と救貧」(『史学』87巻3号、2018年)
- 「近世オスマン帝国の旅と旅人 ―エヴリヤ・チェレビーを中心に」(長谷部史彦編『地中海世界の旅人 ―移動と記述の中近世史』慶應義塾大学出版会、2014年)
- 「一八世紀イスタンブルにおける靴革流通と靴革商組合」(『史学』82巻3号、2013年)
- 「オスマン朝下イスタンブルにおけるイェディクレ周辺の皮鞣工と皮鞣工房群」(『史学』81巻1号、2012年)