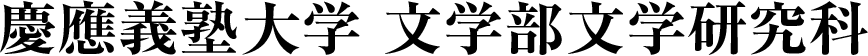French Literature
概要
仏文学専攻は、修士課程が 1951 年(昭和26 年)に、後期博士課程が 1953 年(昭和28 年)に創設されました。すでに約 70 年の歴史と伝統を有することになります。院生は本塾文学部通学課程からの進学者のみならず、通信課程卒業生や他大学出身者なども広く受け入れています。学部を卒業し就職した後、一定の年月を経て大学院で再び学ぶケースもあります。
常時8名前後の教員が授業と論文指導に当たっています。日本人教員は全員がフランスで博士号を取得しています。担当教員の専門は文学と言語学を中心に幅広い分野にわたり、院生の多様な関心や要求に的確に対応できる態勢が整っています。また、院生の研究活動や留学に必要なフランス語の運用能力を育成するため、フランス人訪問教授による徹底した口頭発表の訓練や作文指導も行われています。
修士課程のカリキュラムには、幅広く多様な時代の文学や思想を扱う科目を中心に言語学やフランス語の運用能力を高める科目も設置されています。すべての設置科目を履修し、高度な語学能力を身につけながら、研究者としての視野を広げるよう院生を指導しています。修士課程での学習と研究の成果は修士論文として結実します。
後期博士課程の院生は、明確な研究テーマと方法論により独創性の高い研究活動を続けます。最終的には博士論文の作成と提出、博士の学位取得を目標とします。専攻内で定めた「博士学位請求論文の申請および審査に関する内規」に従い、博士論文が完成するまで指導教授が責任をもって指導に当たります。
毎年一回、秋頃に研究発表会が開催され、修士課程の院生は修士論文の構想を述べ、後期博士課程の院生は研究の進捗状況を報告します。また、研究成果を発表する場として、査読付きの論文集を年一回刊行しています。その編集作業は後期博士課程在学中の院生が担当し、さまざまな業務を体験できるよい機会となっています。
本専攻で扱う学問領域の性質上、院生には留学を積極的に勧めています。これまでに、本塾交換留学制度によりENS(高等師範学校)、ソルボンヌ・ヌーヴェル大学、コート・ダジュール大学、トゥールーズ第1大学などに留学生を送り出してきました。フランス政府給費留学生試験に合格した院生も数多くいます。
修了生は本塾をはじめさまざまな大学で教育や研究に従事しています。高等学校の教員になる者、一般企業や公的機関で働く者もいます。文壇や詩壇などでいわゆる三田派の伝統に連なる執筆活動を展開する小説家、詩人、批評家も少なくありません。
教員
名前/職位
専攻/専門領域/研究内容/主要著作
-
仏文学専攻
現代フランス文学及び思想20世紀のフランス文学および思想を主な研究対象としています。ジョルジュ・バタイユ、モーリス・ブランショ、ジャン=ポール・サルトルらについてのミシェル・フーコー、ジャック・デリダらの考察を参照しながら、実存主義が構造主義、ポスト構造主義によって乗り越えられて行く過程について考察しています。最近は、1980年代のジャン=リュック・ナンシーの共同体論に焦点を絞り、ナンシーによるバタイユ読解の射程やブランショの共同体論との差異について考えています。
主要著作- « Généalogie de l'affirmation de la pensée négative », in A. Milon(ed.), Leçon d'économie générale : l'expérience-limite chez Bataille-Blanchot-Klossowski, Presses Universitaires de Paris Nanterre, 2018
- 「時間、エクリチュール、政治 - ジョルジュ・バタイユとジャン=リュック・ナンシー」,『多様体』no.2, 総特集ジャン=リュック・ナンシー, 月曜社, 2020(ジャン=リュック・ナンシー, 市川崇, 柿並良佑ほか共編著)
- 「ジャン=リュック・ナンシーの「不死性」」, 『思想』12月号 no. 1172, 追悼 ジャン=リュック・ナンシー, 岩波書店, 2021
- ジャン=リュック・ナンシー『否認された共同体』市川崇訳, 月曜社, 2023 (翻訳)
- « La Foi et la démocratie », in Jean-Luc Nancy - Anastasis de la pensée, textes réunis et présentés par D. Dwivedi, J. Lèbre, M. Montévil et F. Warin, Hermann, 2023
-
仏文学専攻
フランス語学主にフランス語を対象とし、意味論と語用論の境界領域の諸現象を分析しています。レトリックや翻訳学にも関心があります。
主要著作- Cognition et émotion dans le langage(共同編著、慶應義塾大学出版会、2006)
- 『プチ・ロワイヤル和仏辞典 第3版』(執筆協力、旺文社、2010)
- « L’argumentativité de la métaphore dans une sémantique argumentative », M. Bonhomme et al. (dir.), Métaphore et argumentation, Editions Academia, 2017
- « Le paradoxe », L. Behe et al. (éds.), Cours de sémantique argumentative, Pedro e João editores, 2021
- « L’interprétation argumentative en contexte », Corela, 22-1, 2024
-

仏文学専攻
19世紀フランス文学ボードレール、ユイスマンスの美術批評を主要な研究対象として、「超自然主義」の系譜に関心をもっています。
主要著作- « De l’impertinence à la certitude morale : Baudelaire et Lautréamont » (Influences de Baudelaire, PUR, 2025, p.227-238.)
- 「モーリス・ブランショの文学時評、ロートレアモンと小説の問題」(『レトリックとテロル ジロドゥ/サルトル/ブランショ/ポーラン』澤田直/ヴァンサン・ブランクール/郷原佳似/築山和也編、水声社、2024年、p.245-264.)
- « L’imagination chez Baudelaire, mouvement et construction » (RHLF, 2019, n°2, p.333-345.)
- « Le naturel dans la théâtralité baudelairienne » (Romantisme, n°179, 2018, p.141-150.)
- « Le poème en prose chez Huysmans : contre la bourgeoisie » (Huysmans et les genres littéraires, PUR, 2010, p.173-182.)
-
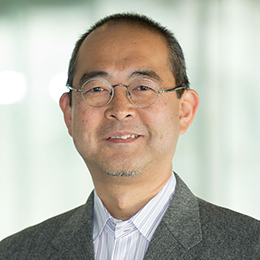
仏文学専攻
近現代フランス文学20世紀の作家ジャン・ジュネの研究に軸足を置いていますが、ほかへの興味も尽きません。刑罰制度の表象については身を入れて調べていますし、「三面記事」、「帰還」、「告白」、「描写」など、ひとつの主題をめぐって複数の作品を読み解いていくことにも愛着をもっています。
主要著作- 『フランス現代作家と絵画』(共編著、水声社、2009)
- ジュネ『公然たる敵』(共訳、月曜社、2011)
- Dictionnaire Jean Genet(共著、Honoré Champion、2014)
- タハール・ベン・ジェルーン『嘘つきジュネ』(単訳、インスクリプト、2018)
- 「所有と携行―ジュネのスーツケース」(『リミトロフ』第4号、2024)