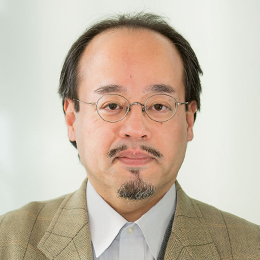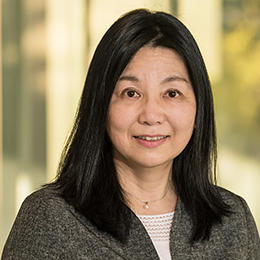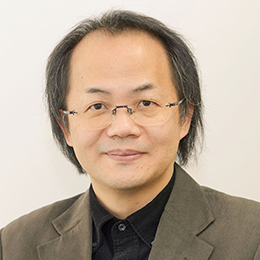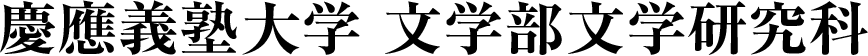美学美術史学分野
Aesthetics and Science of Arts
Aesthetics and Science of Arts
概要
慶應義塾における美学美術史学の歴史は、1892(明治25)年に開講された森鷗外の「審美学」にまで遡ります。当初は美学および西洋美術史から出発しましたが、その後、日本・東洋美術史、西洋音楽史、音楽が関わる舞台芸術一般を研究領域に加え、近年は芸術組織運営、芸術支援などの研究・教育にも積極的に取り組んでいます。
すなわち本専攻には、理論研究(美学・芸術学)、歴史研究(美術史・音楽史・舞台芸術史・現代芸術論)、実学研究(アート・マネジメント)の3つの柱があります。2005(平成17)年度には、この3つの柱を美学美術史学分野とアート・マネジメント分野の2分野に集約し、より充実した教育が行える体制を整えました。なお学生は、在籍する分野と異なる分野に設置された科目を一定の範囲内で履修し、修了に必要な単位とすることが可能です。
美学美術史学分野は、理論研究、歴史研究を行う分野です。美学・芸術学、日本・東洋美術史、西洋美術史、西洋音楽史、舞台芸術史、現代芸術論が研究教育の範囲となります。専任者のほか若干名の非常勤講師が授業を担当し、幅広い分野をカバーしています。修士課程では修士論文の作成が必須です。また、後期博士課程では専門研究者として内外で活躍する人材の養成を目指し、学位論文(課程博士)提出により博士学位を取得する道が用意されています。
教員
名前/職位
専攻/専門領域/研究内容/主要著作
-
美学美術史学専攻
西洋美術史主要著作- 『黎明のアルストピア―ベッリーニからレオナルド・ダ・ヴィンチへ』(共著・責任編集,ありな書房,2018)
- 『魔術の生成学-ピエロ・ディ・コジモからパラッツォ・ピッティへ』(共著・監修解説,ありな書房,2016)
- 「ガリレオと建築―17世紀フィレンツェ建築における『新科学』の影響」(『日吉紀要 人文科学』,第30号,2015)
- 『女性の表象学—レオナルド・ダ・ヴィンチからカッリエーラへ』(共著,ありな書房,2015)
- 『変身の形態学 マンテーニャからプッサンへ』(共著・責任編集,解題ありな書房,2014)
-
美学美術史学専攻
西洋美術史ドイツ近代美術を中心として研究に取り組んでいます。とりわけ19世紀から20世紀への転換期ドイツにおいて社会変革思想と感性的創造行為が独特な仕方で接合した様相を重視し、美術、建築、庭園(造園、庭づくり)、デザイン、さらに身体運動(ダンス、体操)等の相互関連性について芸術学・デザイン学の立場から検討しています。20世紀初頭からドイツ国共和制期の芸術状況が近年の研究における重要な検討対象です。
主要著作- Das Weimarer Bauhaus und die Gartenkunst: Ein Reformversuch von Heinz Wichmann, in: Aesthetics, No. 27, March 2023, pp. 26-41, published by The Japanese Society for Aesthetics.
- 「歩くことは踊ること 二〇世紀初頭ドイツにおける〈躍動〉としての体操」、『ユリイカ』[特集:わたしたちの散歩]2024年6月号、青土社、219-226頁。
- 「庭園芸術が問う技術時代の総合芸術」、『科学と芸術』、中央公論新社、2022年2月、279-298頁。
- 『ドイツ近代造園とゲーテ ―― ヴァイマルの「ゲーテ荘園の庭」修復(1948−49年)を中心に ―― Moderne deutsche Gartenkunst und Goethe. Zur Restaurierung von Goethes Gartenhaus in Weimar (1948/49)』(日独二か国語版)、科研成果論文(課題番号18K18490)、2020年3月。
- Ostwalds Farbenlehre und die Farben von Pflanzen. Uber Farbentafeln im Gartenbau, in: Mitteilungen der Wilhelm-Ostwald-Gesellschaft e. V., 22.Jg. 2017, H. 2, 10-30.
-
美学美術史学専攻
日本美術史日本の近世期、江戸時代の絵画史と版画史が専門で、とくに浮世絵や琳派などの作品や作者が主要な研究対象です。このほか、物語絵や風俗画の系譜に連なる古代・中世から近・現代までの絵画作例全般についても、強い関心を抱いています。さらにその先にある問題として、世界の美術史における日本美術の位置付け、という大きなテーマにも取り組んでいます。
主要著作- 『もっと知りたい歌川広重 生涯と作品』改訂版(東京美術、2024)
- 『勝川春章と天明期の浮世絵美人画』(東京大学出版会、2012)
- 『浮世絵とパトロン』(慶應義塾大学出版会、2014)
- 『うき世と浮世絵』(東京大学出版会、2017)
- 『北斎への招待』(朝日新聞出版、2017)
-

美学美術史学専攻
アーツ・マネジメントアーツ・マネジメント、すなわち、オーケストラ、オペラ、劇団、ダンス・カンパニー、美術館等の芸術組織のマネジメント(=経営)の調査研究と教育に取り組んでいます。日本でも他国でも、芸術組織の多くは非営利あるいは公共の組織となっていることが多く、非営利の芸術組織を中心とした研究ということもできます。
主要著作- 『アーツ・マネジメントの基本』(慶應義塾大学出版会、2021)
- 『アーツ・マネジメント概論 三訂版』(共著、水曜社、2009)
- フランソワ・コルベール著、曽田修司・中尾知彦共訳『文化とアートのマーケティング』(美学出版、2021)
- 「ウルフ・レポートをめぐって: アメリカにおける一九九〇年代前半のオーケストラ経営」『芸術学』第24号(2021)
- 「Democracy in Orchestras (1):Musician Involvement in U.S., British and Japanese Professional Orchestras」『静岡文化芸術大学研究紀要』 Vol. 7(2006)
-

美学美術史学専攻
音楽学、西洋音楽史W. A. モーツァルトを中心とする古典派音楽の研究。モーツァルトの手稿譜の調査を通じて、作品をめぐる諸問題(成立過程、演奏実践、同時代の受容等)を解明しようと考えています。18世紀のウィーンとザルツブルクにおける宮廷楽団、劇場、公開演奏会、楽譜出版についても研究を進めています。
主要著作- 『モーツァルト』音楽之友社、2005年。
- 「ラノワ・コレクションのモーツァルト資料」樋口隆一編著『進化するモーツァルト』春秋社、2007年、197-242頁。
- 「モーツァルト《ト短調交響曲》K. 550の“Corrupt Passage”再考」『新モーツァルティアーナ 海老澤敏先生傘寿記念論文集』音楽之友社、2011年、 320-334頁。
- 「W. A. モーツァルトの演奏用パート譜に関する一考察 -「筆写者二七」のミサ曲史料を中心に-」『芸術学』(慶應義塾大学・三田芸術学会誌)第22号、2018年、pp.27‐49。
- “Die Bassbesetzung in den Serenaden, Divertimenti und Notturni von Michael Haydn”, In Johann Michael Haydn. Werk und Wirkung, Strube Verlag, München, 2010, S. 193-206.
-

美学美術史学専攻
音楽学、西洋音楽史19世紀ロマン主義の作曲家フランツ・リストの音楽、とりわけ宗教的作品が研究対象です。残された手稿譜や書簡などから、作品の成立過程、稿と編曲の関係、さらに作品を取り巻く環境などの解明に取り組んでいます。
主要著作- 『リスト』作曲家 人と作品シリーズ、音楽之友社2005年2月5日。
- Franz Liszt, Cantico di San Fransesco for trombone with pianoforte or organ, Urtext, Liszt Society Publications vol. 13, ed. Wataru FUKUDA, The Hardie Press, 2016, pp. iv-vi, 1-31.
- 「F.リストの宗教音楽における教会旋法の問題」、『音楽学』第41巻Ⅰ号、日本音楽学会、1995年10月 13-32頁
- Franz Liszt’s Cantico del Sol: A Source Study. Studia Musicologica, vol. 61, no. 3–4 December 2020. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 381-396.
- 「フランツ・リストの《教皇賛歌》―「ピウス九世」から「教会の礎」へ―」、『芸術学』2020年24号、三田芸術学会、2021年3月31日、140-169頁"
-

美学美術史学専攻
西洋美術史・芸術学17世紀フランス美術史・美術論。ニコラ・プッサン研究を中心に、プッサンの作品を規範として掲げた17世紀後半の王立絵画彫刻アカデミーにおける美術理論の確立とその変容に関心を持っています。画家の制作論、実際の作品とその受容、作品や画家を巡る言説、社会的文脈、美術コレクションなど、相互に絡み合う様々な要因を考察に加え、研究に取り組んでいます。
主要著作- 望月典子『ニコラ・プッサン― 絵画的比喩を読む』慶應義塾大学出版会、2010年。
- 望月典子『タブローの物語―フランス近世絵画史入門』慶應義塾大学三田哲学会叢書、2020年。
- 望月典子「一七世紀フランス宗教画とgrâceの概念―アンドレ・フェリビアンの美術批評をめぐって―」『美学』(美学会編) 264号、2024年、pp. 73-84.
- 望月典子「セバスティアン・ブルドン〈慈悲の七つの行い〉連作―プロテスタンティズムと一七世紀フランス宗教画―」『美術史』(美術史学会編) 196冊、2024年、pp. 210-226.
- Noriko Mochizuki, "Mars et Vénus de Nicolas Poussin: Sa réception de l'art antique et de la poétique de Marino,'' Dix-Septième siècle (Presses Universitaires de France), no.255, 2012, pp. 341-351.