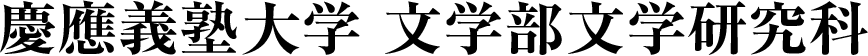Philosophy
概要
哲学分野は、文学研究科に設置されて以来一貫して西洋哲学を追求し、日本の哲学研究の中核を担ってきました。哲学は最も古い学問ですが、その長い伝統と先端の両方を兼ね備えているのが本分野です。哲学のすそ野は広大で、すべてをカバーすることはできませんが、伝統と現代の二点に研究の焦点を定めた点に特徴があります。スタッフは古典研究と現代研究に重点的を置いた陣容になっています。院生は、修士課程と後期博士課程にそれぞれ十数名が在籍し、他大学や他学部からの入学者も珍しくありません。
本専攻の伝統の一つは古代ギリシア・中世の古典研究にあり、プラトン、アリストテレスから中世哲学まで幅広い領域をカバーできる、国内の大学では珍しい充実した陣容となっています。そこでは古代ギリシア語やラテン語が飛び交い、哲学の原点にある諸問題が議論されます。もう一つの伝統は、二十世紀以降の現代哲学の研究です。そのなかでは論理学や言語哲学、科学哲学、現象学といった新しい潮流はもちろんのこと、形而上学や認識論などの古くからの領域もアップデイトされ、分野の垣根を越えた探求が日々進められています。
大学院の授業は、修士課程では修士論文、後期博士課程では博士論文という目標のために、必要な語学や哲学の基本ツールを修得し、さらにそれを磨く場となっています。また、学生は学内外での研究に積極的に参加し、学内における三田哲学会の例会、MIPS(三田哲学会の哲学・倫理学の合同研究集会)での発表、機関誌『哲学』への論文執筆のほか、各々の専門と関連する全国学会での発表、論文投稿など、活動の機会は大きく広がっています。他方で、さまざまな研究プロジェクトも展開されており、教員だけでなく多くの学生もその研究の一端を担う形で参加しています。
また、専任教員と学生の関係にも良き伝統が生きています。相互の信頼を基礎に日々の研究が進められていることはもちろん、授業以外での共同研究、さらには人間的なふれあいも随所に見られます。学生同士での勉強会も多く、相互啓発が活発に行われています。
教員
名前/職位
専攻/専門領域/研究内容/主要著作
-

哲学専攻
現代ドイツ語圏の哲学、哲学的論理学私の現在の研究の柱は、二つです。(1) G・フレーゲの論理哲学、前期ウィトゲンシュタイン哲学、ハイデガーの解釈学的現象学を、いわゆる「形而上学的内部主義」と哲学的言語の可能性の問題をめぐって比較・架橋すること、(2)アリストテレス、カント(『判断力批判』)、ハイデガー、ガダマー、ウィトゲンシュタイン、ライル、アンスコム、マクダウェル、M・トンプソンらを、知識論・言語哲学・行為論における「フロネーシスの伝統」とも呼ぶべき哲学的系譜として描きだすこと。
主要著作- 『世界を満たす論理 —— フレーゲの形而上学と方法——』, 勁草書房, 2019年.
- 『これからのウィトゲンシュタイン——刷新と応用のための14篇』, 荒畑靖宏・山田圭一・古田徹也[編著], リベルタス, 2016年.
- 『世界内存在の解釈学 —— ハイデガー「心の哲学」と「言語哲学」』春風社, 2009年.
- Welt – Sprache – Vernunft, Ergon Verlag, Würzburg, 2006.
- 『あらわれを哲学する――存在から政治まで』, 荒畑靖宏・吉川孝[編著], 晃洋書房, 2023年.
-
哲学専攻
西洋中世哲学西洋中世のキリスト教思想家トマス・アクィナスの思想を存在論や認識論を中心に勉強しています。英米系分析哲学の手法を用いて古典的な問題に新たな光を当てることが面白いと思っています。その他、英米系現代認識論や分析系宗教哲学の分野にも関心を持っています。
主要著作- 『神さまと神はどう違うのか』(ちくまプリマー新書、2023)
- 『現代認識論入門 -- ゲティア問題から徳認識論まで』 (勁草書房、2020)
- ジョン・グレコ、上枝美典訳『達成としての知識 —認識的規範性に対する徳理論的アプローチ』(勁草書房、2020)
- 「トマスにおける神の知の不変性と時間の認識」(『中世思想研究』58号、2016)
- 「現実性としてのエッセ再考」 (『アルケー 関西哲学会年報』21号、2013)
-
哲学専攻
行為論、現代形而上学行為とは何か、合理性とは何か、心とは何か、言語とは何かといった問題や、伝統的な形而上学の諸問題に、いわゆる分析哲学の手法を使って取り組んでいます。と同時に、それらの異なる問題圏を結びつけるルートを探っています。また最近では、価値や人生といった問題にも関心をもっています。
主要著作- 『自己欺瞞と自己犠牲』(勁草書房、2007)
- 「幸福の形式」(戸田山和久・出口康夫編『応用哲学を学ぶ人のために』世界思想社、2011)
- 「自己欺瞞」(信原幸弘・太田紘史編『シリーズ新・心の哲学Ⅲ 情動篇』勁草書房、2014)
- 『コミュニケーションの哲学入門』(慶應義塾大学出版会、2016)
- 『現代形而上学入門』(勁草書房、2017)
-

哲学専攻
時間と心の哲学。記憶の形而上学。ベルクソンおよびライプニッツを中心とする近現代哲学時間におけるマルチスケールという観点に着目し、延長と時制(テンス)のみならず相(アスペクト)を組み込んだ時間哲学を構築しつつ、それを用いて意識・心・自由・記憶といった哲学的諸問題へのアプローチを模索しています。伝統的な哲学テクストに含まれるアイデアを、現代の分析哲学や科学理論の枠組みから再解釈・再定式化することで、哲学史と哲学をより普遍的な思考のツールとすることに関心があります。
主要著作- 『世界は時間でできている ベルクソン時間哲学入門』(青土社、2022)
- 平井靖史・藤田尚志編『〈持続〉の力――ベルクソン『時間と自由』の切り開く新地平』(書肆心水、2024年)
- Yasushi Hirai (ed.) Bergson's Scientific Metaphysics, Bloomsbury 2023.
- 平井靖史・藤田尚志編『〈持続〉の力――ベルクソン『時間と自由』の切り開く新地平』書肆心水、2024年。
- “Does Time Have A Speed? Time Qualia and Bergson’s Durée” Sintese: O PENSAMENTO E O MOVENTE – 90 ANOS. v. 51 n. 160 2024, pp. 245-270.