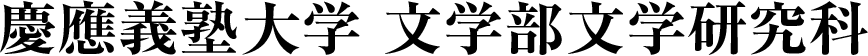Western History
概要
西洋史学分野の修士課程では、以下に紹介する教員の個別研究分野よりやや広い分野で、一次史料や基礎的研究文献を講読し、基礎知識の獲得を目指します。後期博士課程では、身につけた基礎知識を前提として、さらに高度な研究能力を養成します。そして、学位論文の作成を通じて研究者を育成することを目標とします。西洋史は、時間的・空間的に膨大な領域を対象とします。しかし、学部教育と違い大学院、特に後期博士課程では、学生の研究分野と教員の指導できる分野が近接していなければなりません。そういった意味から、以下に各教員の個別研究分野をやや詳しく紹介しますので、参考にしてください。
赤江雄一は、中世ヨーロッパ宗教史および中世イギリス史を専門としています。活版印刷すら存在しなかった中世ヨーロッパにおける大量言説普及装置(マス・メディア)であった説教に注目することで、当時の社会のこれまで知られていなかった側面を明らかにする研究を、ラテン語および中世英語の写本史料を用いておこなっています。清水明子は、ドイツ、バルカン現代史を専門にしています。現在は、ナチス・ドイツのヨーロッパ広域秩序構想と大クロアチア国民国家建設の接点における、権力関係と社会的変容の再構成に取り組んでいます。野々瀬浩司は、スイス及び西南ドイツの宗教改革期を対象に、宗教改革の思想的背景、神学上の諸問題、さらには農奴領主制の変化などを研究していましたが、最近は都市と宗教改革の関係について調べています。山道佳子はカタルーニャの近代社会文化史を専門にしています。現在は18世紀後半から19世紀前半のバルセローナにおける絹を扱う手工業者とその家族を主な対象とし、労働とジェンダーのあり方や地理的社会的モビリティについて、遺言書や結婚契約書、死後財産目録、徒弟契約などの公証人文書から明らかにする研究に取り組んでいます。長谷川敬は、古代ローマ社会経済史を専門とし、特にカエサル征服後のガリアやローマ領ゲルマニアの商人、職人、運送業者が、どのような人的ネットワークを構築していたのかを、主に碑文史料から明らかにすることを目指しています。舘葉月は、近現代フランス史と国際関係史を専門とし、スイス・ジュネーヴに拠点を置く赤十字国際委員会の活動をつうじて、第一次世界大戦期とその後のヨーロッパにおける人道主義の展開を研究してきました。また、未曽有の規模になった戦争が終結後も長く社会の様々な面に与え続けた影響を、フランス社会を対象に考えています。
教員
名前/職位
専攻/専門領域/研究内容/主要著作
-
西洋史学専攻
西洋中世史グーテンベルクがヨーロッパに導入した活版印刷に先立って、カトリック世界において大量言説普及システム(マス・メディア)として機能していた托鉢修道会の説教を、歴史学的に研究してきました。文学、哲学・神学、美術史等など密接に関連した研究テーマであるため、中世研究のひろい枠組みを意識しています。現在は、大学等で高度な学問的訓練を受けつつ民衆にも語られた知の形式としての説教を糸口として、中世後期から近世にかけての宗教・文化・政治・学問の絡み合う知的風景を探索しています。
主要著作- ʻJohn XXII as a Wavering Preacher: The Popeʼs Sermons and the Norms of Preaching in the Beatific Vision Controversy’, in Communicating Papal Authority in the Middle Ages, ed. by Minoru Ozawa, Thomas W. Smith, and Georg Strack (Routledge, 2023), pp. 41-61(「揺らぐ言葉と説教者の権威──教皇ヨハネス22世の至福直観の教義をめぐる説教」関西学院大学キリスト教と文化研究センター編『ことばの力──キリスト教史・神学・スピリチュアリティ』関西学院大学キリスト教と文化研究センター 2023年, 55-82頁)
- 赤江雄一・岩波敦子編『中世ヨーロッパの伝統―テクストの生成と運動―』慶應義塾大学出版会, 2022年(「はじめに」i-v頁;「西洋中世における説教術書の伝統生成―説教術書は制度的ジャンルか」3-20頁)
- Pastoral Care and Monasticism in Latin Christianity and Japanese Buddhism (ca. 800 - 1650), co-edited with Toshio Ohnuki, G. Melville, and Kazuhisa Takeda, Vita regularis: Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter - Abhandlungen 84 (LIT, 2024)
- A Mendicant Sermon Collection from Composition to Reception: The ‘Novum opus dominicale’ of John Waldeby, OESA (Turnhout: Brepols, 2015)
- ジョン・H.アーノルド『中世史とは何か』図師宣忠との共訳, 岩波書店, 2022年
-

西洋史学専攻
ドイツ現代史・ユーゴスラヴィア史ナチズムがヨーロッパ周縁の多民族社会にもたらした支配体制の実態と地域の権力関係、社会変容を明らかにする研究を進めています。ドイツとバルカンにおける国民統合、「民族共同体」構築やネイション形成プロセスの解明につなげ、「国民国家」をめぐる議論にも向き合います。
主要著作- Die deutsche Okkupation des serbischen Banats 1941-1944 unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Volksgruppe in Jugoslawien (Münster: Lit-Verlag, 2003) 487pp.
- 「バルカンにおける負の連鎖−ボスニア内戦を中心に」『「対テロ戦争」の時代の平和構築−過去からの視点,未来への展望』(東信堂,2008年)
- 「ナチス・ドイツ傀儡『クロアチア独立国』のセルビア人虐殺(1941〜42年)」および「クロアチア『祖国戦争』と『民族浄化』(1991〜95年)」『大量虐殺の社会史−戦慄の20世紀』(ミネルヴァ書房,2007年)
- 「スロヴェニア人の移動」および「第二次世界大戦中のナチ・ドイツとバルカン」『中欧・東欧文化事典』(丸善出版、2021年)
- K.カーザー『ハプスブルク軍政国境の社会史』(共訳、学術出版、2013)
-
西洋史学専攻
スイス宗教改革史、農村社会史これまで宗教改革的な新しい神学が近世ヨーロッパ社会に与えた影響について、実証的に考察してきました。特にドイツ農民戦争期の抗議書を史料として用いて、平民が抱いていた「神の法」思想の分析を行い、16世紀のスイスや西南ドイツにおける農奴制問題と宗教改革運動との関わりを研究しました。最近では、宗教改革期の戦争観や都市と宗教改革の関係についての研究を開始しました。
主要著作- 『ドイツ農民戦争と宗教改革:近世スイス史の一断面』(慶應義塾大学出版会、2000)
- 「ドイツ農民戦争期におけるチューリヒの農奴制問題について」(『西洋史学』197号、2000)
- 「宗教改革者と農奴制:ベルンの再洗礼派の例を中心にして 」(『西洋史学』212号、2004)
- 『宗教改革と農奴制:スイスと西南ドイツの人格的支配』(慶應義塾大学出版会、2013)
- 浅見雅一氏との共編著『キリスト教と寛容:中近世の日本とヨーロッパ』(慶應義塾大学出版会、2019年2月28日公刊、総数277頁)
-
西洋史学専攻
スペイン(カタルーニャ)近代史スペインの中でも独自の歴史・文化・言語を持つ地域(ネーション)のひとつであるカタルーニャの近代史を研究しています。ここ数年の研究テーマは、18世紀後半から19世紀初頭のバルセローナ市の絹織物及び絹に関わる手工業の職人の世界(仕事、家族、信仰)を、職人とその妻や寡婦の遺言書・死後財産目録・結婚契約書などの史料から再構築することです。なかでも特に現在は、ストッキング製造業者に焦点をあてて調べています。授業では、これまで勉強してきた都市形成、祭り、スポーツなど、カタルーニャの社会文化史に関わるさまざまテーマや、カタルーニャの独立運動の現状などを、広く紹介しています。
主要著作- 『近代都市バルセロナの形成:都市空間・芸術家・パトロン』(共著、慶應義塾大学出版会、2009)
- 「ギルド社会における職業と家族:産業革命前夜のバルセローナにおける絹産業」(『スペイン史研究』28号、2014)
- 「産業化以前のバルセローナにおける家業と女性(1770−1820)ー絹産業ギルドの親方・職人とその妻、寡婦、娘たちの「結婚契約書」「遺言書」からー 」(『史学』89巻4号、2021)
- (共著)"Silk textiles, crisis and adaptative strategies in Catalonia, 1770-1850s (Barcelona and Manresa) ", Continuity and Change, vol.35-no.1, 2020.
- (共著)"Migración y género en las familias artesanas de Barcelona, 1770-1817", Investigaciones de Historia Económica/Economic History Research, vol. 19, 2023.