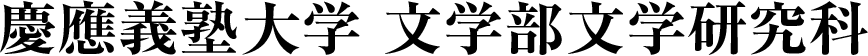大学院文学研究科では、卓越した研究者と高度の専門性を備えた職業人の育成をめざして、学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)、教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)、入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)の3つのポリシーを掲げています。
各専攻・分野では、下記の3つのポリシーを基本として、具体的にそれぞれのポリシーを定めています。詳しくは各専攻・分野のページをご覧ください。
修士課程
卒業認定・学位授与の方針
(ディプロマ・ポリシー)
<教育目標>
慶應義塾大学の卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)を前提として、課程修了時に学生が身につけるべき能力として以下のものを定め、これらを身につけ、先導者として全社会に貢献しうる人材の養成を目標とする。加えて、教育課程において定める所定の要件を満たした学生に対し、修士(哲学)、修士(美学)、修士(史学)、修士(文学)、修士(日本語教育学)、修士(図書館・情報学)のいずれかの学位を授与する。
<資質・能力目標>
- ⑴専門とする分野において、研究領域全般に関する専門知識を身につけ、適切な研究方法とそれぞれの専門において必要となる諸言語を駆使して専門的な研究を展開し、その成果を母語や外国語で発表する力。
- ⑵専門とする分野における特定テーマに関して修士論文を執筆し、さらに、修士論文のテーマに関連する領域については包括的な専門知識を有し、その領域の研究に貢献する力。
- ⑶専門研究を通じて人間、文化、社会を考えるとともに、重要な問題や課題を認識し、それを解決するための議論や実践を行うことができ、高度なリテラシーと批判的分析能力を備えた研究者、教育者、実務家として社会に貢献する力。
- ⑷社会の中で人文学を学ぶことの意義を自覚し、自ら設定した目標の達成や社会問題の解決を、ふさわしい方法で行う力。
教育課程編成・実施方針
(カリキュラム・ポリシー)
<教育課程の編成>
文学研究科は、「卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)」に掲げる資質・能力を養成するために、特殊講義科目、特殊講義演習科目、研究科目のほか、各専攻において適当と認める授業科目から構成される教育課程を体系的に編成する。
<教育課程の実施>
この教育課程の編成のもと、以下の教育方法を組み合わせて教育を実施する。
- ⑴文学研究科全体のカリキュラムの基盤として、各専攻・分野において修士課程の全在学期間を通じて履修可能な、母語ならびに外国語による少人数演習科目を設置する。
- ⑵修士論文の執筆を可能とするため、指導教員の個別論文指導と演習授業を通じ、研究テーマについての知識を深めるとともに、高度な研究能力および論述力を養う。また、修士論文中間報告会等の機会を設けて、複数の教員から指導を受ける機会を提供する。
- ⑶海外の大学院への正規留学によって取得した単位を修了要件に含めることを、単位数を限って認める。また、文学研究科独自の支援制度により留学を援助する。
- ⑷海外への留学等を念頭において、より柔軟な履修を行えるように全ての科目は半期科目として開講する。
- ⑸領域横断的な研究を可能とするために、慶應義塾大学大学院の他研究科および附属研究所の設置科目、さらに文学研究科と提携関係にある他大学院の設置科目を修了要件として履修することを、単位数を限って認める。
<学修成果の評価方法>
本研究科の教育課程により修得すべき資質・能力目標に対する学修成果の評価は、全塾としてのアセスメントプランの考え方のもと、各科目において定める成績評価基準等に基づいた直接的な指標により行われるほか、各種アンケートや調査等を含めた定量的・定性的、直接的・間接的な指標を用いて評価される。具体的には、①学生による授業評価、②休学や退学の状況などを用いる。
修士論文審査については、論文題目に加えて、主査(原則として指導教員)と2名の副査で構成される審査団の文学研究科委員会による承認、審査団による論文審査、審査団および関連教員による口頭試問を経て、最終的な審査結果を文学研究科委員会で審議、承認する。
<資質・能力目標と教育内容との関係>
- ⑴専門とする分野において、研究領域全般に関する専門知識を身につけ、適切な研究方法とそれぞれの専門において必要となる諸言語を駆使して専門的な研究を展開し、その成果を母語や外国語で発表する力。
→特殊講義科目、特殊講義演習科目、研究科目において、専門知識と研究方法を着実に身につけるとともに、研究内容を発信するための言語力を養う。 - ⑵専門とする分野における特定テーマに関して修士論文を執筆し、さらに、修士論文のテーマに関連する領域については包括的な専門知識を有し、その領域の研究に貢献する力。
→特殊講義科目、特殊講義演習科目、研究科目および個別論文指導において、修士論文執筆に必要な、研究領域についての学識を深めるとともに、高度な研究能力および論述力を養う。 - ⑶専門研究を通じて人間、文化、社会を考えるとともに、重要な問題や課題を認識し、それを解決するための議論や実践を行うことができ、高度なリテラシーと批判的分析能力を備えた研究者、教育者、実務家として社会に貢献する力。
→特殊講義科目、特殊講義演習科目、研究科目、専攻によっては実験、フィールドワークにかかわる科目を組み合わせて履修することにより、研究・学習課題を自ら定め、達成する能力を育成する。 - ⑷社会の中で人文学を学ぶことの意義を自覚し、自ら設定した目標の達成や社会問題の解決を、ふさわしい方法で行う力。
→特殊講義科目、特殊講義演習科目、研究科目、専攻によっては実験、フィールドワークにかかわる科目を組み合わせて履修し、さらに他研究科および附属研究所の設置科目、文学研究科と提携関係にある他大学院の設置科目の履修も可能とし、広く人文科学領域に関する理解を深める機会を設ける。
入学者受入れの方針
(アドミッション・ポリシー)
<求める学生像>
- ⑴卒業論文執筆や専門科目の履修等を通じて自身の専門領域についての理解を深め、専門とする領域全般についての基礎知識を有している。
- ⑵大学院において何をどのような方法で研究したいのかという研究計画、あるいは専門的な知識やスキルの修得をキャリアにどのように活かせるかについて具体的な計画を自ら考え、まとめることができる。
- ⑶諸言語の一次資料および二次資料を正確かつ批判的に読むことができる基礎的な読解力、学術的内容を的確に論じることができる基礎的な表現能力を身につけている。
- ⑷修士課程修了後の研究者、教育者、実務家としてのキャリアについて、積極的に考えている。
<選抜の基本方針>
このような入学者を幅広く受け入れるため、一般入試により選抜を実施する。
- ⑴一般入試
専門科目・指定言語科目・選択言語科目の三科目の試験および口頭試問による選抜であり、文学研究科にふさわしい高い学力を要求する。ただし、言語科目のない専攻・分野、指定言語科目もしくは選択言語科目のない専攻・分野がある。
後期博士課程
卒業認定・学位授与の方針
(ディプロマ・ポリシー)
<教育目標>
慶應義塾大学の卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)を前提として、課程修了時に学生が身につけるべき能力として以下のものを定め、これらを身につけ、先導者として全社会に貢献しうる人材の養成を目標とする。加えて、教育課程において定める所定の要件を満たした学生、あるいは博士論文審査に合格した者に対し、博士(哲学)、博士(美学)、博士(史学)、博士(文学)、博士(図書館・情報学)のいずれかの学位を授与する。
<資質・能力目標>
- ⑴専門とする研究分野について博士論文を執筆し、その論文を通じて、当該領域の研究に独創的な寄与を成す力。
- ⑵研究対象とする分野において、最新の研究動向や研究課題に精通し、包括的で深い専門知識を有し、母語や外国語で国際的に成果を発信してその分野の研究に独自の貢献をする力。
- ⑶専門研究を通じて人間、文化、社会を深く洞察するとともに、重要な問題や課題を発見し、それを解決していくための高度な研究を行うことで、高度なリテラシーと批判的分析能力を備えた研究者、教育者、実務家として社会に独自の貢献をする力。
- ⑷社会の中で人文学を学ぶことの意義を自覚し、自ら設定した目標の達成や社会問題の解決を、ふさわしい方法で行う力。
教育課程編成・実施方針
(カリキュラム・ポリシー)
<教育課程の編成>
文学研究科は、「卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)」に掲げる資質・能力を養成するために、特殊研究科目、特殊研究演習科目のほか、各専攻において適当と認める授業科目から構成される教育課程を体系的に編成する。
<教育課程の実施>
この教育課程の編成のもと、以下の教育方法を組み合わせて教育を実施する。
- ⑴専門とする分野の研究に独創的な貢献をする博士論文の執筆を可能とするため、指導教員が担当する科目を中心とした履修を行うとともに、指導教員が中心となって個別に論文指導を行い、高度な研究能力を養う。
- ⑵専門とする領域において最新の研究動向や研究課題に精通し、独自の貢献をするために必要な高度な研究能力を養成するため、後期博士課程の全在学期間を通じて履修可能な母語や外国語による少人数演習科目を設置し、その履修を修了要件とする。研究成果を学会や学術専門誌で発表することを目的として具体的な指導を行う。
- ⑶文学研究科ならびに慶應義塾大学国際センター等を通じての留学を推奨する。また、文学研究科独自の支援制度により留学を援助する。
- ⑷海外への留学等を念頭において、より柔軟な履修を行えるように、全ての科目は半期科目として開講する。
- ⑸研究分野のより専門的な研究を可能とするために、海外の大学院への正規留学によって取得した単位を修了要件に含めることを、単位数を限って認める。
- ⑹後期博士課程の学生の高度に専門的な研究を推進するために、海外の著名な研究者に副指導教員としての指導を依頼し、文学研究科委員の指導教員との共同指導のかたちで博士論文を準備することができる。
<学修成果の評価方法>
本研究科の教育課程により修得すべき資質・能力目標に対する学修成果の評価は、全塾としてのアセスメントプランの考え方のもと、各科目において定める成績評価基準等に基づいた直接的な指標により行われるほか、各種アンケートや調査等を含めた定量的・定性的、直接的・間接的な指標を用いて評価される。具体的には、①学生による授業評価、②休学や退学の状況などを用いる。
博士学位取得のためには、学生は専攻、分野が定めた博士論文執筆資格審査に合格し、博士論文を文学研究科委員会に提出して受理される必要がある。さらにその後1年以内に、文学研究科委員会で承認された主査と副査によって論文が審査され、文学研究科委員会に報告された審査報告に基づき、文学研究科委員の投票によって合格しなくてはならない。
<資質・能力目標と教育内容との関係>
- ⑴専門とする研究分野について博士論文を執筆し、その論文を通じて、当該領域の研究に独創的な寄与を成す力。
→特殊研究科目、特殊研究演習科目および個別論文指導において、博士論文執筆に必要な、研究領域についての学識を深めるとともに、高度な研究能力および論述力を養う。 - ⑵研究対象とする分野において、最新の研究動向や研究課題に精通し、包括的で深い専門知識を有し、母語や外国語で国際的に成果を発信してその分野の研究に独自の貢献をする力。
→特殊研究科目、特殊研究演習科目において、専門知識と研究方法を高度なレヴェルで身につけるとともに、研究内容を発信するための言語力を養う。 - ⑶専門研究を通じて人間、文化、社会を深く洞察するとともに、重要な問題や課題を発見し、それを解決していくための高度な研究を行うことで、高度なリテラシーと批判的分析能力を備えた研究者、教育者、実務家として社会に独自の貢献をする力。
→特殊研究科目、特殊研究演習科目、専攻によっては実験、フィールドワークにかかわる科目を組み合わせて履修することにより、研究・学習課題を自ら定め、高度なレヴェルで達成する能力を育成する。 - ⑷社会の中で人文学を学ぶことの意義を自覚し、自ら設定した目標の達成や社会問題の解決を、ふさわしい方法で行う力。
→特殊研究科目、特殊研究演習科目、専攻によっては実験、フィールドワークにかかわる科目を組み合わせて履修し、さらに他研究科および附属研究所の設置科目、文学研究科と提携関係にある他大学院の設置科目の履修も可能とし、広く人文科学領域に関する理解を深める機会を設ける。
入学者受入れの方針
(アドミッション・ポリシー)
<求める学生像>
- ⑴自分の研究領域および関連分野について、高度な専門的知識を有している。
- ⑵修士課程における専門的研究をふまえて、博士論文につながる独創性のある具体的な研究計画を自ら考え、まとめることができる。
- ⑶諸言語の資料を正確かつ批判的に読むことができる分析的な読解力、学術的な論述力を身につけている。
- ⑷後期博士課程修了後の研究者、教育者、実務家としてのキャリアについて、積極的かつ具体的に考えている。
<選抜の基本方針>
このような入学者を幅広く受け入れるため、一般入試により選抜を実施する。
- ⑴一般入試
専門科目・指定言語科目・選択言語科目の三科目の試験および口頭試問による選抜であり、文学研究科にふさわしい高い学力を要求する。ただし、言語科目のない専攻・分野、指定言語科目もしくは選択言語科目のない専攻・分野がある。